| (質問) | 物理化学とはどんな学問ですか? (化学科 K君) |
||||
| (返答) | 「物理化学」とは、単なる「物理」と「化学」の境界領域的な学問だと往々にして認識されがちですが、 まったく異なる独創的な分野です。 一言で言えば「世の中に起こる全ての現象を分子レベルで理論立てて説明する学問」です。 「物事の本質を突き詰める学問」と置き換えても良いかもしれません。 「AとBを混ぜたらCになった!」のではなく、「何故、Cになったのか?」 と、まず考えるのが物理化学的な考え方です。 つまり、定性的(現象が起きたかどうかALL or NOTHING の考え方)ではなく 定量的(現象が起きた規模がどの程度か数値化する考え方)に物事を考えていきます。 原因を追求することで、 「では、こうやったらDになるな。」とか、「こうやったらZが出来るかも。」など 次のステップ(具体的には新規物質の開発や新法則の確立)を考える学問です。 |
||||
| (質問) | 具体的にはどのように考えるのですか? (化学科 Lさん) |
||||
| (返答) | 分子レベルで現象を理解するためにはまず分子の性質を知る必要があります。 どのような形をしているのか?(異性体、キラル、パッキング、体積) どれくらい重いのか?(分子量) どれくらい力があるのか?(分子間力、静電力、クーロン力、磁力) 好きな物、嫌いな物はあるのか?(疎水性、親水性) どれくらいすばやいか?(反応速度、活性化エネルギー) どれくらい丈夫か?(生成熱、安定性、自由エネルギー変化) ・・・などなど それこそ友達や恋人を理解するかの如くです。 (頑張っても理解しきれないのも似ている・・・。) ある一つの分子について上のような性質を知り、もう一つの違う分子の性質を知ることで、 その二つが出会った時に生じる物語(化学反応、分子間相互作用)を予感するのです。 |
||||
| (質問) | 具体的にはどのようなことを調べているのですか? (理学科 M君) |
||||
| (返答) | 例えば水を例にとってみると、 水(液体)は温度と圧力を変えることによって、氷(固体)になったり、水蒸気(気体)になったりします。 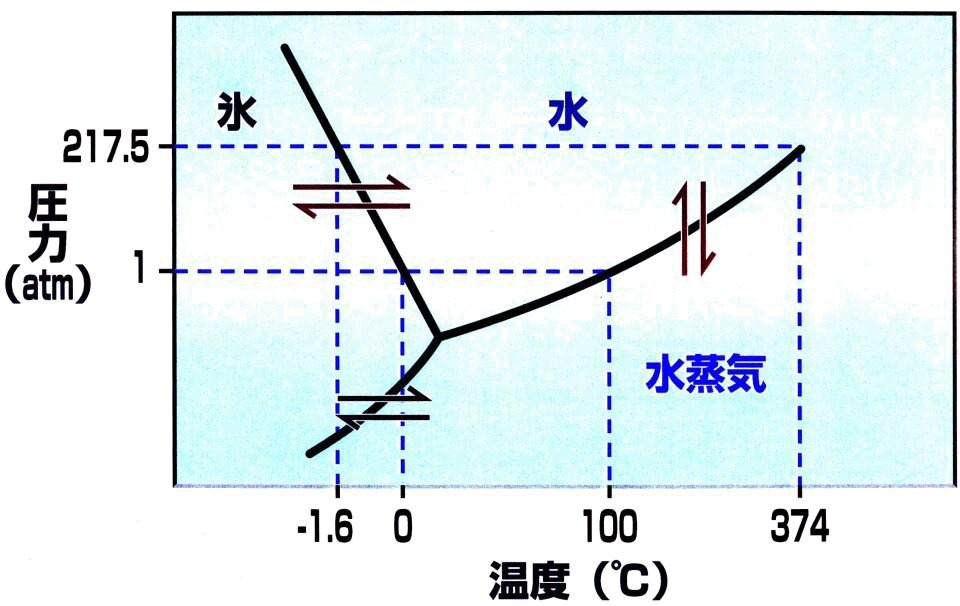 図 水の状態図 これは上の返答で示したような水分子の様々な性質によって決まっているのです。 1種類の分子ならまだ話は分かりやすいですが、これが2種類、3種類となってくると、 それぞれの性格や相性(分子間相互作用)が絡み合い、複雑な様相を呈します。 例えば固体のAという分子を液体のBという分子に溶かしたら、 ・どのくらい熱がでるのか?(発熱、吸熱) ・どのくらい体積が変わるのか?(膨張、収縮) ・どんな色になるのか?(光の吸収、構造変化) など様々な現象を調べることができます。 我々はそのような関係を明らかにし、あらゆる事象の根本原理を紐解くために、 分子の構造やエネルギーや体積などの熱力学量を定量的に詳しく調べています。 |
||||
| (質問) | 具体的に測っている対象は何ですか? (化学科 Aさん) |
||||
| (返答) | この少ないスペースで簡単に答えるのは難しいのですが、 液体では 水、アルコール類、DMSO、FAMSO、キラル溶液 固体では シクロデキストリン、アミノ酸、酵素・タンパク質(様々な生物由来のもの)、 デオキシコール酸、フラーレン、キラル結晶、製剤 などがあります。 これらを単体だけではなく複合して測ることにより、 「液体が混ざるとは何か?」 といった本質的な疑問から 「生命現象とは何か?」といった複雑な問題まで考えています。 また、単純なサンプルだけではなく、 ・微生物や粘菌、細胞、筋肉などの代謝エネルギーの測定 ・熱測定による昆虫の生態サイクル解明 ・ヒフ細胞への化粧品の効果 ・生体内医療器具の適合性決定 ・異常原子価化合物の状態決定 ・アモルファス度の高精度決定 など、熱測定を応用した生活感あふれる研究も行っております。 何故これらの系を測ると分かるのか? の問いに答えるにはあまりにもスペースが足りません。 是非、我々物理化学研究室に直接足をお運びください。 |
||||
| (質問) | それは何の役に立つのですか? (化学科 C君) |
||||
| (返答) | 例えば単純な水とアルコール類について調べると、 「どのような物質が水に溶けやすいのか」を定量的に表すことができます。 その情報を基にすることによって、油のような水に溶けにくい物質を水に溶かすための 有効な方法を創出することが出来ます。 これは新規な洗剤の開発や溶けにくい薬の改良に大いに役に立ちます。 また、酵素やタンパク質の溶液中での構造を調べると、 「どのような構造がどのような機能をもつ」のかが明らかになり、 ポストゲノムの一環として人工酵素の開発にも大いに利用できます。 物理化学で明らかにする現象は主にモデル系(基本的な系)であるため、 その応用分野を多岐に渡すことができます。 他には何か役に立たないの? の問いに答えるにはあまりにもスペースが足りません。 是非、我々物理化学研究室に直接足をお運びください。 |
||||
| (質問) | どのような装置で調べるのですか? (化学科 T君) |
||||
| (返答) | 物理化学研究室で用いられる測定装置は大きく分けると以下のように分類されます。 熱量測定(静的測定) ・超高感度滴定型微少熱量計 ・超高感度固体反応測定熱量計 ・伝導型微少溶解熱量計 ・等温壁型溶解熱熱量計 熱分析(動的測定) ・熱重量-質量分析 ・示差走査熱量計 蒸気圧測定 ・沸点型気液平衡測定装置 ・静的気液平衡測定装置 ・蒸気圧浸透計 密度測定 ・振動式精密密度計 ・高温・高圧対応振動式精密密度計 粘度測定 ・高精度粘度測定装置 ・高精度回転型粘度測定装置 分光測定 ・円二色性測定装置 (大学院研究室) ・蛍光測定装置 (大学院研究室) ・紫外可視吸光度測定装置 試料精製関連 ・スピニングバンド型精留塔 ・へリックスパッキング型精留塔 ・カールフィッシャー型含水量測定装置 ・ガスクロマトグラフィー+質量分析 などがあります。 また、実験だけではなく、コンピュータシミュレーションによる理論計算や量子化学計算ももしています。 これらの装置は一から手作りのものや、市販の装置を改良したものばかりで、 市販品よりも精度を高めております。 |
||||
| (質問) | 物理化学は数式が多いと聞いたのですが本当ですか? (質問多数) |
||||
| (返答) | 化学という分野から見ると確かに多く感じるかもしれませんが、たいしたことはありません。 また、別に試験というわけではないのですから、 わからなくなったら、教科書を見ながら先輩方に相談して、 一つ一つ理解していけばよいのです。 この世の中最後は定量的な数値で判断します(しなければなりません(生産性、生活費等々) 食わず嫌いだったものが意外に美味しかったということがあるでしょう? (いつも自然に使っていますよね 数学) |
||||
| (質問) | 就職先はどんなところが多いですか? (質問多数) |
||||
| (返答) | 先に示したように物理化学的な考え方は多分野に応用できるためか、 (それともそういう人が集まってくるためか、) 就職先も人それぞれバラエティに富んでいます。 ちなみに本年の場合、 化学系研究員、MR、コンピュータ関連、SE、飲食関連、 また大学院や教員志望もおります。 今年は4人もの卒業生が先生(中学 高校)になりました。 色々勉強できる雰囲気があるのでしょう。 特に色々な基礎を自分のものにすることができるためではないかと考えております いずれにしても、就職は本人の意志で決まるもの。 就職を希望している人は、はっきりとした自分の意見を早めに確立して活動に臨んで下さい。 卒業研究と就職活動を両立していくのは大変ですが、 これを乗り切らないと、到底社会の荒波には太刀打ちできません。 また、物理化学研究室は大学院生も募集しております。 研究内容に興味がある方は是非ご連絡ください。 |
||||
| 分かりやすさを第一に答えておりますので、科学的に不適当な表現はご了承ください。 | |||||